業務を改善したり、新しい計画を立てたりするときには、感覚や経験だけに頼らず、「見える化」されたデータや図を使って冷静に判断することが大切です。この記事では、業務を分析するための代表的な手法と、データを図表・グラフで可視化するための考え方やツールを整理して解説します。
1. 業務の課題を洗い出す分析手法

この章では、業務のどこに問題があるのか、どのポイントに優先的に手を打つべきかを整理するための代表的な分析図を紹介します。これらは「業務分析手法」と呼ばれ、業務計画を立てる前の現状把握に役立ちます。
パレート図
パレート図は、原因や項目ごとの発生件数や金額を大きい順に並べ、棒グラフと折れ線グラフを組み合わせた図です。「重要な少数」と「取るに足らない多数」を見分けるのに適しており、不良原因やクレーム理由など、改善の優先順位を決めるときに使われます。
ABC分析
ABC分析は、売上高や在庫金額などの指標に基づいて、対象をA・B・Cの3ランク程度に分類する方法です。例えば在庫管理では、金額の大きいAランクの品目を重点管理し、Cランクは簡易な管理にすることで、限られた管理コストを有効に使うことができます。
特性要因図(フィッシュボーンチャート)
特性要因図は、魚の骨のような形をした図で、問題(特性)に対して考えられる原因(要因)を枝分かれさせて整理します。人・機械・方法・材料・環境などの切り口で要因を列挙することで、抜け漏れなく原因候補を洗い出すことができます。
ロジックツリー
ロジックツリーは、問題や目標をツリー状に分解し、「なぜ?」や「どうやって?」を繰り返して論理的に構造化する図です。売上不振の原因を「客数」と「客単価」に分け、さらにその下を掘り下げるなど、思考の抜けを防ぐのに役立ちます。
コンセプトマップ
コンセプトマップは、概念同士の関係を線でつなぎながら図にしたもので、知識の構造を整理する手法です。業務フローの中で「顧客」「問い合わせ」「対応履歴」などの概念をつなぎ、全体像を共有する場面でよく使われます。
パレート図や回帰分析を使った業務改善
パレート図で重要な要因を特定し、回帰分析で「どの要因がどれくらい結果に影響しているか」を数値的に確認すると、説得力ある改善案を示せます。たとえば「特定の作業時間を10%短縮すると、全体のリードタイムが何%短くなるか」といった効果を推計し、業務改善の根拠として説明できます。
2. プロセスとスケジュールを管理する図解
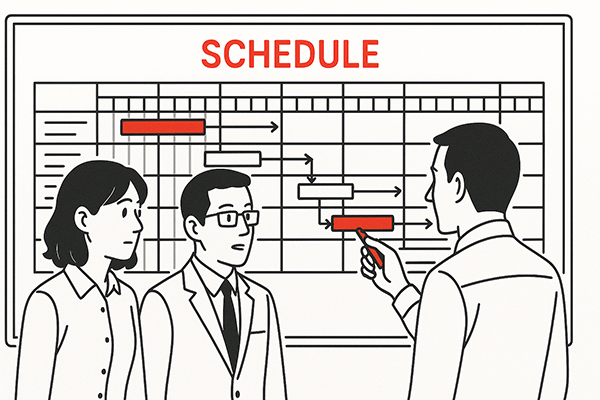
この章では、業務プロセスや品質、プロジェクトの予定を管理するために使われる図解手法を扱います。業務計画を立てる際に、どの作業をいつまでに、どの順番で行うかを考えるときに有効です。
管理図
管理図は、製品やサービスの品質が一定の範囲に収まっているかを時系列で監視するための図です。平均値と上限・下限の管理限界線を引き、点がその範囲から外れたら異常の兆候として原因調査を行います。製造業だけでなく、サービス業のリードタイム管理などにも利用できます。
系統図
系統図は、目的を達成するための手段や要因を、木の枝のように段階的に展開して整理する図です。「顧客満足の向上」という目的から、「応対品質の向上」「待ち時間の短縮」などを枝分かれさせて整理することで、具体的な施策に落とし込みやすくなります。
PERT(アローダイアグラム)
PERTは、作業と作業の順序関係を矢印で表したネットワーク図です。どの作業が終わらないと次に進めないか、どこに余裕があるかを視覚的に把握できます。アローダイアグラムと呼ばれることも多く、大規模なシステム導入などのプロジェクト計画で活用されます。
クリティカルパス分析
クリティカルパス分析は、PERTで表したネットワークの中から「全体の工期を決める最も時間のかかる経路(クリティカルパス)」を見つける手法です。クリティカルパス上の作業が遅れるとプロジェクト全体が遅れるため、重点的に管理すべき作業として把握できます。
3. 数値データを読み解く統計的アプローチ

この章では、数値データを扱うときに重要となる統計的な考え方と、その結果を表現するための図を解説します。業務データから傾向や関係性を読み取る上で欠かせない要素です。
最小二乗法
最小二乗法は、散布図上のデータ点と直線とのずれ(二乗誤差)が最も小さくなるように、近似直線を求める方法です。売上と広告費の関係などを直線で表し、将来の値を予測する際の基礎となります。
回帰分析
回帰分析は、ある変数(目的変数)が、他の変数(説明変数)によってどのように影響を受けるかをモデル化する手法です。単回帰分析や重回帰分析を通じて、「残業時間が増えるとミスがどれくらい増えるか」など、業務の因果関係を推定します。
相関と因果
相関とは、2つの変数の間に一緒に増減するような関係があることを指しますが、それだけでは「原因と結果(因果)」があるとは限りません。例えば、アイスの売上と海水浴客数には相関がありますが、互いが直接の原因ではなく、気温という別の要因が影響している可能性があります。
擬似相関
擬似相関は、実際には直接の因果関係がないのに、第三の要因の影響などで強い相関があるように見えてしまう状態です。データ分析の結果を鵜呑みにせず、背後にある要因や環境を考える視点が重要になります。
散布図
散布図は、2つの数値データを縦軸と横軸にとり、点としてプロットした図です。点の分布の傾きや広がりを見ることで、変数同士の相関の有無や程度を直感的に把握できます。
相関係数行列
相関係数行列は、複数の変数同士の相関係数を表形式で一覧にしたものです。売上、広告費、来店客数など、複数指標の関係をまとめて確認する際に便利で、どの組み合わせに強い関係がありそうかを素早く見つけられます。
散布図行列
散布図行列は、複数の変数の組み合わせごとに散布図を並べたものです。相関係数行列よりも視覚的で、どのペアに直線的な関係がありそうか、非線形のパターンがないかなどを直感的に読み取ることができます。
箱ひげ図
箱ひげ図は、データの分布(中央値、四分位数、外れ値など)をコンパクトに表現する図です。部署ごとの処理時間のばらつきを比較するなど、評価対象の安定性や偏りをチェックするときに有効です。
ヒストグラム
ヒストグラムは、データをいくつかの区間に分け、それぞれの件数を棒の高さで表したグラフです。処理時間や販売数量の分布の形(山が1つか複数か、偏りがあるか)を把握し、業務の特性を理解する手がかりになります。
4. 基本のグラフでデータを可視化する

この章では、日常的に使うことが多い各種グラフ・チャートを整理します。目的に応じて適切な可視化手法を選ぶことで、他者にデータを分かりやすく説明し、不適切なグラフにだまされない力も身につきます。
棒グラフ
棒グラフは、カテゴリごとの量を比較するのに向いたグラフです。店舗別売上や部署別人数などを示すとき、長さの違いで直感的に大小関係が伝わります。
折れ線グラフ
折れ線グラフは、時間の経過に伴う値の変化を表すのに適しています。月別売上や日別アクセス数など、推移を見せたいときに利用されます。
複合グラフ
複合グラフは、棒グラフと折れ線グラフなど、異なる形式のグラフを組み合わせたものです。売上を棒、利益率を折れ線で同時に示すように、異なる指標を一つのチャートで比較できます。
2軸グラフ
2軸グラフは、左右に異なる目盛りを持つグラフで、単位の異なる2つのデータを同じ図に表示します。ただし、目盛りの取り方によって印象が大きく変わるため、誤解を招かないよう注意が必要です。
レーダーチャート
レーダーチャートは、複数の評価項目を放射状の軸として表し、項目間のバランスを見るのに適しています。店舗のサービス品質を「スピード」「丁寧さ」「提案力」などで比較する場面で利用されます。
マトリックス図
マトリックス図は、縦軸と横軸に項目をとり、その交点に評価や関係性を記入する図です。製品と市場、要員とスキルなど、二次元で組み合わせを整理するのに役立ちます。
モザイク図
モザイク図は、カテゴリの組み合わせごとの割合を、面積の違いとして表したグラフです。性別と購入有無など、クロス集計の結果を視覚的に示すときに使われます。
クロス集計表
クロス集計表は、2つ以上の項目の組み合わせごとの件数や割合を表にまとめたものです。アンケート結果を「年代×性別」などで分析する際の基本となります。
分割表
分割表は、クロス集計表の一種で、カテゴリデータ同士の関係を分析するために使われます。統計的な検定と組み合わせ、項目間に有意な関係があるかどうかを判断する場面もあります。
ヒートマップ
ヒートマップは、表のセルを色の濃淡で表現し、値の大小やパターンを直感的に把握できるようにした図です。アクセスログの時間帯別・曜日別の分布など、傾向を一目でつかむのに適しています。
チャートジャンク
チャートジャンクとは、3D表示や過度な装飾など、情報量を増やさないのに見た目だけを派手にした要素のことです。チャートジャンクが多いグラフは、かえってデータの解釈を妨げたり、誤解を生んだりするため、避けるべきとされています。
5. データ形式とツールの選択・活用

この章では、データを扱う際のファイル形式や、それを処理・可視化するツールの考え方をまとめます。目的に応じたツール選択と、優れた可視化の事例についても触れます。
CSV(Comma Separated Value)
CSVは、カンマ区切りで項目を並べたテキスト形式のファイルで、多くの表計算ソフトやデータベースで扱える汎用的な形式です。異なるシステム間でデータをやり取りする際の基本フォーマットとして広く利用されています。
シェイプファイル
シェイプファイルは、地理情報システム(GIS)で用いられる代表的なファイル形式で、地物の形状や属性情報を保存します。店舗の立地や顧客分布などを地図上に可視化するときに活用されます。
共起キーワード
共起キーワードは、文章中で一緒に現れることが多い単語の組み合わせを指します。問い合わせメールやSNSの投稿を分析し、「不具合」と共に現れやすいキーワードを調べることで、顧客の不満の焦点をつかむことができます。
データの図表表現(チャート化)
データの図表表現、つまりチャート化は、数値やテキスト情報を表やグラフに変換して、直感的に理解できるようにすることです。単なる数字の羅列よりも、トレンドや差異を短時間で把握できるようになります。
図表やグラフによるデータ分析
図表やグラフは見せるだけでなく、分析にも用いられます。散布図で相関を確認したり、ヒストグラムで分布を確認したりすることで、統計的な分析結果を視覚的に理解しやすくなります。
利用目的に応じたツールの選択
分析や可視化を行うツールには、表計算ソフト、BIツール、統計ソフト、GISソフトなど多様なものがあります。大量データを扱うのか、リアルタイム表示が必要なのか、地図表示が必要なのかといった目的に応じて、適切なツールを選ぶことが重要です。
データの整理・検索・分析・加工・表現のためのツールの利用
ツールは、データの整理や検索、分析、加工、表現といった一連のプロセスを効率化してくれます。たとえば、データベースで必要なレコードを抽出し、表計算ソフトで加工し、BIツールで可視化するといった流れを構築することで、業務全体のスピードと精度が向上します。
優れた可視化の事例
優れた可視化の事例としては、次のようなものがあります。
多次元の可視化では、多くの指標を色・形・位置などを組み合わせて表現し、複雑なデータを一度に把握できるようにします。関係性の可視化では、ネットワーク図などを用いて人や組織、要素間のつながりを表します。挙動・軌跡の可視化では、顧客の移動経路や操作ログの変化を時間軸で示し、行動パターンを理解します。リアルタイム可視化では、ダッシュボードを使って最新の業務状況を常に監視します。テキストデータの可視化では、ワードクラウドやネットワーク図で文章の特徴を把握し、大量のテキストから傾向をつかむことができます。
まとめ
業務分析と業務計画では、目的に応じて適切な手法や図を選び、データを分かりやすく可視化することが重要です。パレート図や特性要因図で課題を洗い出し、PERTやクリティカルパス分析で計画を立て、統計的な手法や各種グラフで結果を検証することで、論理的で説得力のある業務改善が可能になります。さらに、CSVやシェイプファイルなどのデータ形式やツールを上手に活用し、チャートジャンクを避けた分かりやすい可視化を行うことで、関係者全員が同じ認識で議論できるようになります。


コメント