企業は、たくさんの人や部署が関わり合いながら仕事を進めています。その全体のしくみが「経営組織」です。この記事では、代表的な組織形態の種類と、近年よく聞く「CxO」の意味までを整理し、どのような考え方で組織がつくられているのかを分かりやすくまとめます。
1. 経営組織とは何かを押さえよう

この章では、経営組織の基本的な役割と、なぜさまざまな組織形態が存在するのかを確認します。組織の形には必ず狙いがあり、その違いを理解することが大切です。
経営組織の役割
経営組織の役割は、企業の目標を効率よく達成するために、仕事と権限、責任を分担し、調整することです。誰がどの仕事を担当し、誰が意思決定を行うのかが明確になっているほど、仕事はスムーズに進みます。逆に、組織の設計が悪いと、重複作業や責任の押し付け合いが起こり、成果が出にくくなってしまいます。
組織設計で意識する視点
組織を設計するときは、「意思決定のスピード」「専門性の高さ」「現場への権限移譲」「部門間の連携」など、いくつかの観点のバランスを考えます。すべてを同時に満たす完璧な形はないため、企業の規模や事業内容、成長段階に応じて、最適な組織形態を選ぶことが重要です。
2. 基本となる組織構造のパターン
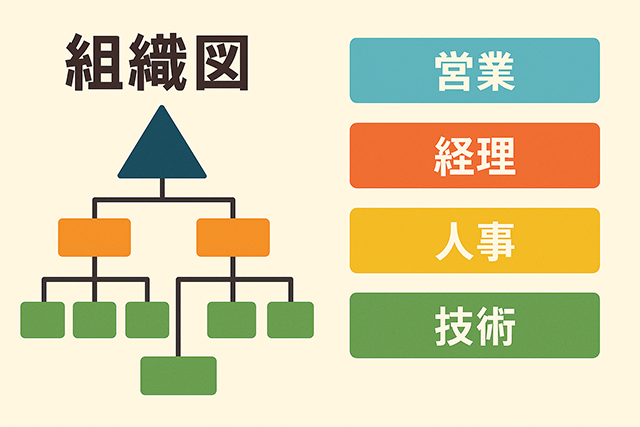
ここでは、もっとも基礎的な組織構造である「階層型組織」と、その中で仕事の分け方によって生まれる「機能別組織」「職能別組織」を説明します。多くの企業は、まずここからスタートし、必要に応じて他の形態へと発展させていきます。
階層型組織
階層型組織は、上から下へと権限と責任が流れるピラミッド型の構造です。社長の下に取締役、その下に部長・課長・係長・担当者というように、明確な指揮命令系統が作られます。指示のルートが分かりやすく、大規模組織でも統制しやすい一方、意思決定に時間がかかりやすいという短所があります。
機能別組織
機能別組織は、「営業」「製造」「開発」「人事」「経理」など、企業内の機能ごとに部署を分ける形態です。同じ機能を担当するメンバーがまとまるため、専門性を高めやすく、業務の標準化も進めやすい特徴があります。ただし、機能ごとに縦割りになりやすく、部門間の連携が弱くなるおそれがあります。
職能別組織
職能別組織は、技術職・営業職・事務職など、職種や職能ごとに構成する組織形態です。似た職種同士でスキルを伸ばしやすく、人材育成の面でメリットがあります。一方で、顧客や製品単位での横断的な視点が弱くなり、全体最適よりも自分の職能の都合を優先してしまうリスクがあります。
3. 事業ごとに分ける組織形態

この章では、製品や地域などの「事業単位」で組織を分ける形態を扱います。多角的に事業を展開する企業が、スピード感を持って意思決定するために採用しやすい構造です。
事業部制
事業部制は、製品別・地域別・顧客別などの単位で「事業部」を作り、それぞれがある程度独立して収益責任を持つ形態です。たとえば「国内事業部」「海外事業部」「新規事業部」といった分け方が挙げられます。市場の変化に素早く対応しやすい一方、事業部ごとに似たような機能が重複し、コストが増える可能性があります。
カンパニー制
カンパニー制は、事業部制をさらに進めて、社内に「社内カンパニー」と呼ばれるほぼ独立した会社のような単位を設ける仕組みです。各カンパニーは自らの戦略や投資を決める裁量を持ち、業績責任も負います。自律分散的に事業を進められますが、全社としての一体感やシナジーをどう保つかが課題になります。
持株会社
持株会社は、グループ各社の株式を保有し、全体の経営方針を決める会社です。実際の事業活動は、子会社や関連会社が担います。持株会社は資本面やガバナンス面からグループ全体を統括し、事業ごとの独立性とグループとしての戦略性を両立させる役割を果たします。一方で、組織構造が複雑になり、管理コストが増える可能性があります。
4. プロジェクトを軸にした柔軟な組織

この章では、開発や新規事業など、期間限定の仕事を進めるために使われる組織形態を扱います。変化の激しい環境では、これらの形態をうまく組み合わせることで、機動力の高い組織運営が可能になります。
プロジェクト組織
プロジェクト組織は、特定の目的や期間のために、さまざまな部署からメンバーを集めて編成されるチームです。新製品開発やシステム導入、拠点立ち上げなど、ゴールが明確な仕事に向いています。プロジェクト完了後は解散するのが一般的です。専門性を横断的に組み合わせられる一方、元の部署との調整や、メンバーの評価方法に工夫が必要です。
マトリックス組織
マトリックス組織は、「機能(職能)軸」と「事業(プロジェクト)軸」の二つの線が交差する構造です。社員は、たとえば「技術部門」と「製品Aプロジェクト」のように、二人の上司を持つことになります。組織の柔軟性と情報共有には優れていますが、指示がぶつかりやすく、権限や責任の線引きを明確にする必要があります。
5. 経営幹部の役職名とCxOの意味

この章では、組織のトップに位置する「CxO」と呼ばれる役職名を説明します。グローバル企業の影響もあり、日本企業でも英語表記の役職名を使うケースが増えています。
CxOという考え方
CxOとは、「Chief × Officer」の総称で、企業の特定領域における最高責任者を表す肩書きです。xの部分に担当分野を入れ、「CFO(最高財務責任者)」「CHRO(最高人事責任者)」など、さまざまなバリエーションがあります。会社全体の戦略をそれぞれの専門領域からリードする立場だと理解すると分かりやすくなります。
CEO(最高経営責任者)
CEO(Chief Executive Officer)は、最高経営責任者を意味します。企業の最終的な意思決定や業績に責任を持つ立場であり、日本企業の「社長」「代表取締役」に近いイメージです。株主や取締役会との関係は国や企業によって異なりますが、組織のトップとして経営全般を統括します。
CIO(最高情報責任者)
CIO(Chief Information Officer)は、情報システムやIT戦略の最高責任者です。単に社内システムを運用するだけでなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革したり、情報セキュリティを強化したりする役割も担います。デジタル化が進む中で、その重要性は年々高まっています。
まとめ
経営組織は、企業の目標を達成するために人と仕事をどう配置し、どのように意思決定していくかを定める枠組みです。階層型組織や機能別・職能別組織は、安定した運営に向いている一方、多角化が進むと事業部制やカンパニー制、持株会社など、事業単位で責任を持つ形態が採用されることがあります。
一方、新製品開発や新規事業など、変化の激しい領域では、プロジェクト組織やマトリックス組織のように、部署をまたいだ柔軟な体制が効果的です。どの形態にも長所と短所があり、企業の状況に応じて組み合わせて使うことが実務上のポイントになります。
さらに、組織のトップに立つCEOやCIOといったCxOは、それぞれの専門分野から企業全体の方向性を示す役割を担っています。組織図の形だけでなく、誰がどの領域の最終責任を持つのかを理解することで、経営組織の姿がより立体的に見えてきます。こうした視点を持っておくと、実際の企業事例に触れたときにも、なぜその組織構造が選ばれているのかを考えやすくなります。


コメント